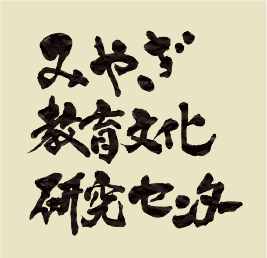未来可能性について考える26
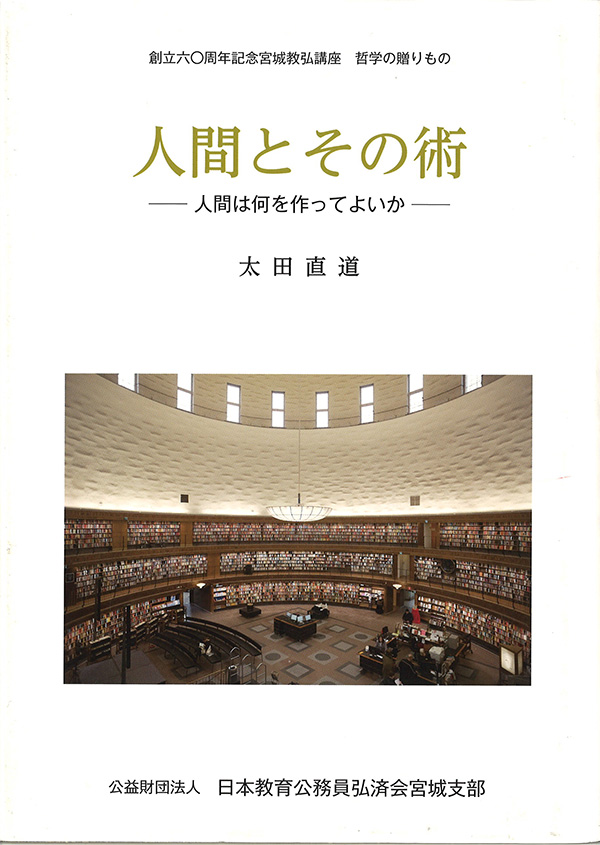
| 日 時 | 2025年10月20日(月) 13:30~16:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 太田直道 著『人間とその術』 |
| 内 容 | テキスト『人間とその術』と太田先生作成の補足資料を読み合い、その内容について意見交流しながら学習して行きます。テキストは、毎回1節ずつ読み進める予定でいます。 |
| 前回の 様子 |
9月は、テキスト第9講の2「 美的世界の創造としての制作」にある、「美意識について」「製作行為について」、そして「イメージとファンタジー」を読み進めました。 太田先生は「美意識について」の冒頭、現代芸術は美の世界から後退しているのではないか。芸術における美的体験は可能かと問いかけ、その問いに対して、人が美意識を持つことは人間精神における根本事実であり、美的内容はさまざまでも美意識なしでは、いかなる行動にも立ち上がることはできないと述べる。だとすると冒頭の問いに対する応えは、現代においても美意識を持ち、美的体験も依然として可能ということになろう。 次に「制作的行為について」では、芸術制作は人間精神の本来の姿を垣間見せるという。その際に制作行為を担っているのは、知性とか意思ではなく、純粋受動というべき感情(美的感情)であり、制作の隠された重心は、作り出すことのうちにではなく、待ち受けることにあるのではないかという。この美的感情に関わっては、西田幾多郎の『藝術と道徳』を引用しながら、その純粋感情は芸術制作を貫いており宇宙的感情、生命感情と呼ぼうとも述べている。 最後の「イメージとファンタジー」では、あらゆる芸術制作は心象世界としてのイメージが心に生まれることから始まる。イメージの中でも架空的、幻想物語的な内容に満たされたものがファンタジー(美的想念)であり、現実世界に対するもう一つの世界を開くと述べた。太田先生はイメージを喚起する働きをするのが想像力であり、目をつぶって見るのがイメージ。一方、目を開いて見るのは物理的な現実世界で、そこで働くのは知性だと説明した。 それから美的想念の根底には生命イメージがあるとして阿部次郎の『美学』も引用した。 |