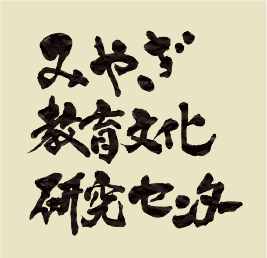『教育』を読む会 10月例会
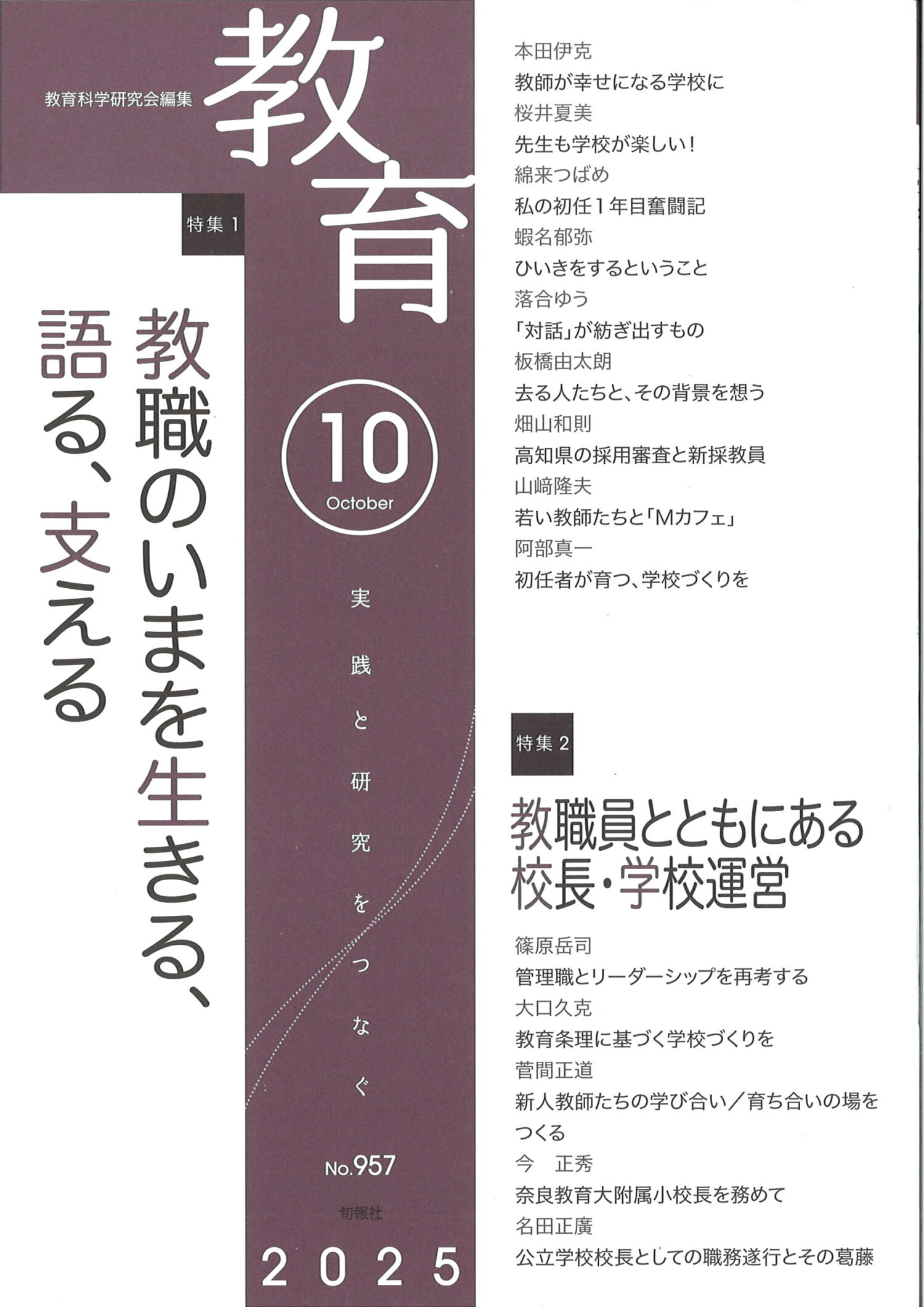
| 日 時 | 2025年10 月11日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| テキスト | 『教育』2025年10 月号 |
| 内 容 | 【10月号】 教師受難の時代と言われたりする。しかし教師を続ける以上、目の前には子どもたちとそして仕事が待っている。 |
| 前回の 様子 |
宮城『教育』を読む会2025年9月例会 9月20日(土)10時~12時に、みやぎ教育文化研究センターで『教育』を読む会を開催しました。参加者は少なめでしたが、深い議論ができました。 |