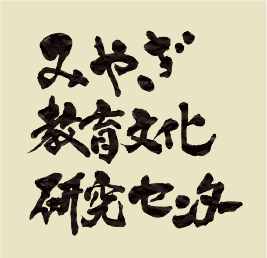『教育』を読む会8&9月例会
.jpg)
| 日 時 | 2025年9月20日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 『教育』2025年8&9月号 |
| 内 容 | 【8月号】 【9月号】 8月は、夏休みですが、みなさん様々な研究会や学習会に参加のため忙しく日程調整ができませんでした。というわけで、9月に8・9月号を一緒に扱うことになりました。そんな欲張りなことができるかは大変あやしいのですが、まずはやってみて、それから次を改めて考えることにしました。 さて8月号の特集1では、阪神・淡路大震災、東日本大震災、北海道胆振東部地震、能登半島地震の当事者の声を伝えます。教育、学びとして、各種の災害とどのように向き合うことができるのか。そこに向かう第一歩として、被災体験の「継承」について考えます。特集2では、学校現場に「〇〇スタンダード」が広がり浸透するなかで、創造的な授業実践を行うことが困難になってきています。ここでは、教科書を軽視することなく、教科書をバネにした創造的な授業の糸口をさぐります。 9月号の特集1と2では、「子ども・青年の自治の力を育てる」と題して、日本の教育の特色でもある特別活動(学級活動、生徒会活動、学校行事)を取り上げ、民主的な社会の形成者として求められる力の形成について、理論と実践の両面からその役割と課題を明らかにすることをめざします。 |
| 前回の 様子 |
7月の例会は、参議院選挙の話も交えながら『教育』7月号の特集1「戦争体験の継承と平和教育」、特集Ⅱ「地球沸騰化時代のわたしたちⅡ」のとびらを読んだ上で、自由に意見交換しました。 特集1は、加害者としてもかの戦争に携わらざるをえなかった当事者の語りも含め、戦争体験の多層性を示している点に、関心をもって読みました。日本国憲法が、天皇制国家体制に対する根本的な反省のもとに、戦争の放棄、軍事力の不保持を掲げたこと、解釈改憲の積み重ねによって大国主義化が進んでもなお、憲法は一度も改正されていないこと。このことの重みを子どもたちと考え合う社会科の教育実践の取組みについて紹介もあり、語りを通じてしか戦争を知りえない世代が何を継承していくべきか。現に、子どもたちもウクライナやガザなどの戦争を目の当たりにしている状況のなかで何ができるか、考えさせました。 特集2に関しては、日本における気候変動教育の、教員養成課程も含めた取組みの弱さ(三谷高史論文)、二酸化炭素排出量の割合の大きい産業部門、運用部門の排出量の削減を、家庭における削減とどう連動させるか(山田一貴論文、79頁)、そのために、「庁」から「省」に昇格したにもかかわらず環境規制に関わる不作為が目立つように感じられる環境行政の取組みも重要になってくることなどを話し合いました。(文責:本田伊克) |