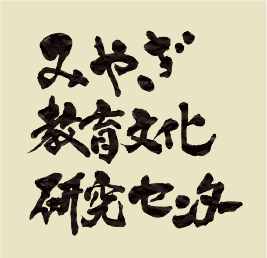『教育』を読む会6月例会
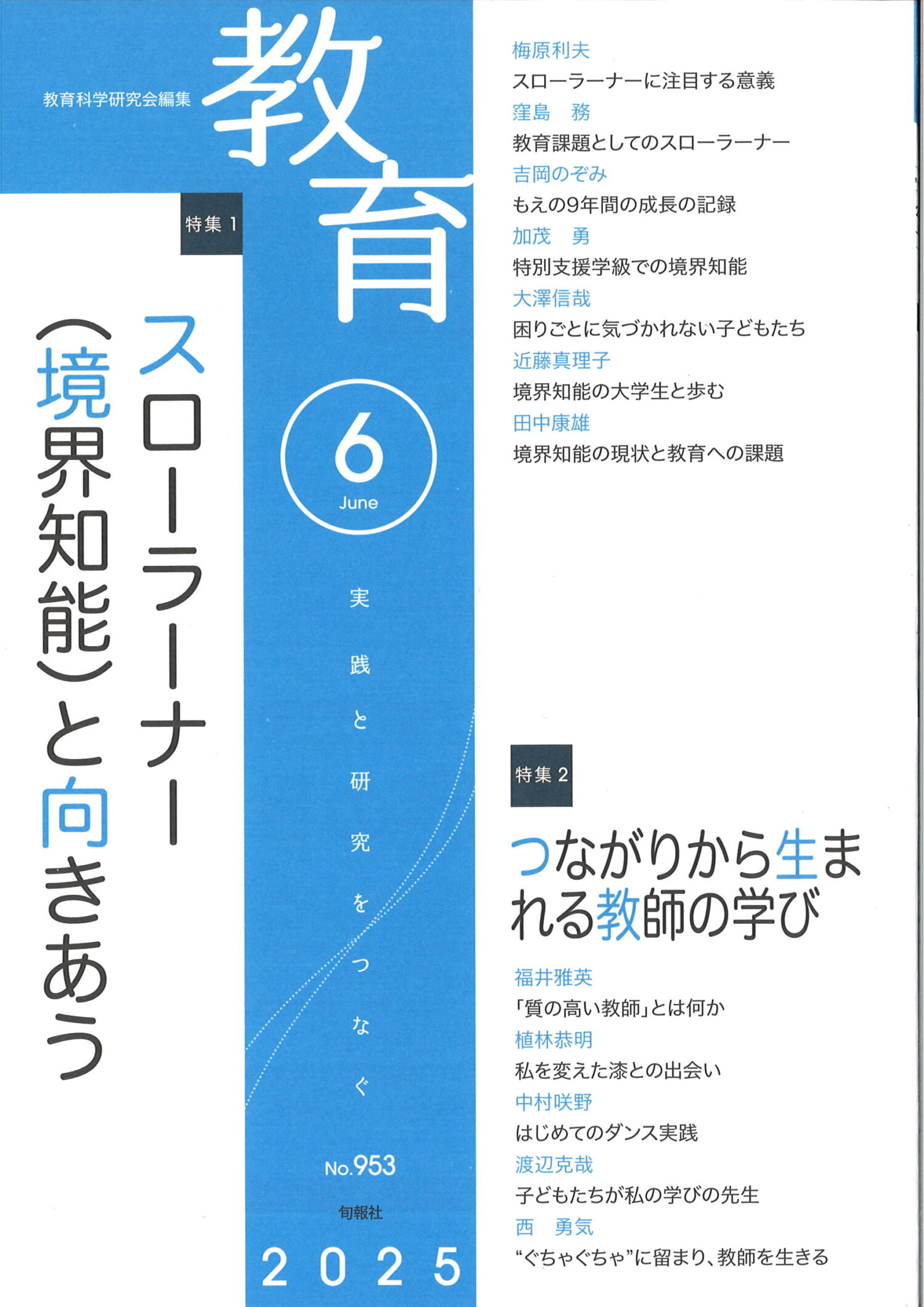
| 日 時 | 2025年6月21日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 『教育』2025年6月号 |
| 内 容 | 【6月号】 特集1では、スローラーナーを特集する。スローラーナーは、医学や心理学では「ボーダーライン知的機能」とも呼ばれている。すなわちIQ70~85の「境界知能」は知的障害ではなく、学齢児の約14%が該当し、35人学級なら約5人いる計算になる。近年、社会の急激な変化や不況・貧困・コロナ禍などを背景に、境界知能の子ども・若者の「生きづらさ」が改めて注目されている。 教師は、成長・発達していく子どもを前に、教師としての生き方や力量が問われ、それらを高めるために学ぶことが求められる。しかし今の学校現場は、日々の業務に追われ、教師からは学ぶ機会や活力が奪われ、効率のよい授業をすることやトラブルのない日常を過ごすことが求められている。だからこそ、特集2では、“教師の学び”について考えたい。 |
| 前回の 様子 |
宮城『教育』を読む会2025年5月例会 5月31日(土)、みやぎ教育文化研究センターで『教育』を読む会を開催しました。参加者は5名と少なかったものの、深い議論ができました。 |