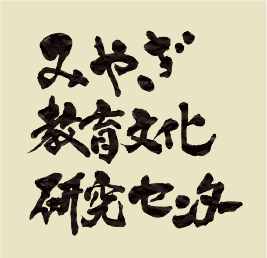4月の例会では、特集1から神代健彦さんの「教育が導く世界、教師が綯いあわせる世代」を輪読し意見交流しました。ここでは神代さんの論考の簡単な要約と、一参加者として神代さんの論考を読みながら考えたこと、思ったことの断片を紡いでみました。
神代さんは、特集1の他の論稿が学校現場からそれぞれの教育実践に即して教師の魅力について語られることから、自身は大学研究者として「日常では意識されない抽象的・象徴的な教職の意味や価値を語ることにします」と論を起こし、主に以下の二つの点から教師の存在と魅力について論じた。
一つは、近年の教育哲学・思想研究では「世界」というキーワードが活発に議論されているとし、今井康雄の「世界への導入」やオランダの教育哲学者ガート・ビースタが「教えることの」の復権を説いていること、さらにはその両者の源泉の一つにH・アレントの『人間の条件』があると言及しながら、教育とは①人間が作り出してきた人間的な世界の事柄を学習者に分かち伝えること《人間の世界を維持すること》と、②既存の世界が子どもたちを押しつぶしてしまわないように保護すること《その人間の世界に新しい世代(子どもたち)を導くこと》だと説く。
二つには、そうした教育を通じての世代交代がどのようになされるかについてイギリスの社会人類学者T・インゴルドの議論や中内敏夫の学力論に拠りながら、世代交代という営みを「地層のように一挙に切り替わるのではなく、時間の経過とともに藁の束が縄として編みあわせられながら長くなっていく」縄綯いのイメージとして捉えなおし、「縄綯い」としての教育を「古い世代が古い世代なりにチャレンジしてきた世界の維持と革新、最良の意味での現在と未来を作り出そうという営みに、新しい世代の参加を促す」ことだと言う。
また、それゆえに、そのような営みに参与する教師という存在は「過去と現在を出会わせ、より合わせ、未来の世界を維持すると同時に新しくしていく人々である」として、教師には高い力量が要求されもするのだと論じた。
・論考で語られている「世界」は、もっぱらわたしたちの生きる現実の外的世界についてであり、その外的世界への参加と関わって教育が論じられ位置づけられている。それが間違っているとは思わないのだけれど、「世界」というキーワードを考えたとき、他方には人間の内的世界(精神世界)がある。その内的世界と教育を、あるいは二つの「世界」の関係を熊代さんはどのように考えているのだろうか。
・なぜ内的世界(精神世界)が気になったのかと言えば、熊代さんは論考で、中内敏夫を引きながら《教育とは、いわばそうした過去の人間が「モノやモノゴトに処する」仕方を、教師という援助者に導かれる(教えられる)ことを介して、新しい世代の人間が追体験すること、そのことを通じて力を獲得していくプロセスだ》と記しているからであり、そのプロセスとしての教育の少なくない部分は人間の内的世界(精神世界)に関わることであり、1日の教育活動の大部分を占める授業という営みと深く関わると思ったからである。
・熊代さんは、論考の軸にH・アレントを置いている。アレントが今日の教育学の中でどのように位置づけられ、また論じられてるのかはわからないが懐かしく思った。アレントと教育に関わる論考にはじめて接したのは、94年6月号の『教育』の小特集「知とまなび」にあった小玉重夫さんの「〈学び〉の社会性と〈教え〉の公共性」だったと記憶している。内容の詳細は忘れたが、興味深く読んだことは覚えている。熊代さんの論考を読みながら、そのことを思い出し、改めて読んでみたいと思った。
・さらに熊代さんの論考を読みながら思い出したのは、アンパンマンならぬ三上満(マン)さんの〈現在(いま)とは、いまだ過ぎ去っていない過去と、もうすでにやってきている未来とのたたかいの場だ〉との言葉。教育は過去と未来とに関わってその二つをつなぎ・せめぎ合う、まさに今・ここにおいて営まれる大きな歴史的事業なのだと。そしてそういう魅力と責任が教育という仕事にはあるのだ改めて思った。
|
.jpg)