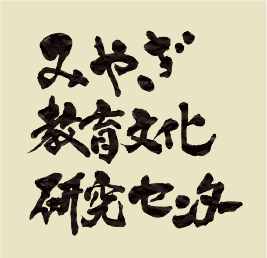2025年宮城『教育』を読む会2月例会の感想
2月22日(土)の10:00~12:00に、みやぎ教育文化研究センターで『教育』を読む会を行いました。
今回は。2025年2月号の特集1「戦争の記憶と平和教育」について、一盛真論文「平和教育とナショナリズム」をまず輪読し、それから話し合いをしました。
扉のことばには、「私たちに刷り込まれている戦争の記憶を相対化する」必要があり、その先に「アジアの人々の信を得る日本の『平和教育』が生まれる」(4頁)とあります。
一盛論文にある「犠牲者意識ナショナリズム」の問題は、水野博子論文(「オーストリアの過去、蘇る記憶」)におけるオーストリアの「犠牲者テーゼ」(15頁)の指摘、さらに、その後に続く各論文、特に、平井美津子論文(「李鶴来の人生から考える戦後補償」)が触れている、日本による強制的な命令によって加害者であることを余儀なくされた、いわば「二重の被害者」の存在など、もっぱら日本人の被害と苦労だけで戦争が語られ、かつ、そのように語られた戦争への認識が世代を超えて刷り込まれていくことの問題性を明らかにしています。
2024年3月末の中学校教科書検定結果で、令和書籍教科書が異例の経緯を経て合格しました。本文を「国生みの神話」から始めるこの教科書は、広く採択されることは少なくとも当面はないかもしれません。しかし、令和書籍の教科書が採択対象になったことで、これよりは極端な主張をしていないという意味でより「まとも」に見えてくるが、実際には日本による加害の歴史に正面から向き合わない歴史観に基づく教科書が、全国の学校に広まる余地はむしろ拡大したと言えるでしょう。
さらに、一盛論文が取り上げる米子市立山陰歴史館の展示において、被害にあった朝鮮人の存在が明記されていないことは、「日本の戦争像と朝鮮人の存在を無とする戦後の精神構造」の問題(12頁)にある点についても、その通りだと思います。
話し合いのなかでは、台湾やドイツでは、自国が何をなしてきたかについて、歴史を語れることが教養であるとされていること、日本・中国・韓国間で戦争と平和に関する共同研究もあるが、日本は、お互い「共感はできなくても共生する」という姿勢よりも、「他国に自らの立場への共感を広げる」姿勢の方が強いのではないかという意見も出ました。
一盛論文では、「平和教育がナショナルなもとなってしまっている」点と、「国外と国内の戦場における<加害>と国民の<被害>というような二元論に陥りがちな認識」の問題が指摘されています(6頁)。
読み深めていくなかで、そもそも「ナショナルなもの」あるいは「ナショナリズム」をどのように捉えるべきか。「ナショナルなものでない」平和教育という場合、どのようなものを思い浮かべればよいのか。
参加者の教員からは、なかなか平和教育に時間が取れないなかで、その必要性は感じつつも、教師も生徒も「もやもや」してしっかりと胸に「落ちない」ような状況で、「平和教育とナショナリズム」となると、「しっかり時間も取れないし、扱いも中途半端になりそうだから、やめておくか」という考えになってしまわないか、という率直な感想も出されました。小学校教員経験者からは、小学校6年生でこの問題を扱うことの難しさも語られました。
また、<加害>と<被害の>二元論に関しては、むしろ、<加害>と<被害>の「重層性」というべきではないか。その方が、私たちの記憶から失われつつある多くの「李鶴来」を忘れないという認識と行動上の課題をより的確に表現できるのではないかという指摘もありました。
また、授業のなかでこうした問題を扱うとき、この特集が指摘するような「被害者ナショナリズム」の立場で多くのことを調べてきた生徒の「知識」の量に、より問題をまともに考えているが、知識や根拠が不足しているためにかえって言い負かされてしまうことも想定されるのではないかという意見もありました。これは、特集2が扱う「他者・社会につながる国語教育」についても当てはまる部分があるように思います。
さらに言えば、「理論武装」と周到な戦略をもっているナショナリスト勢力に、平和を守ることの大切さを認識し、次世代に伝えていくべき私たちの知識と行動も問われていくという感想ももちました。
(文責:本田伊克)
|
.jpg)