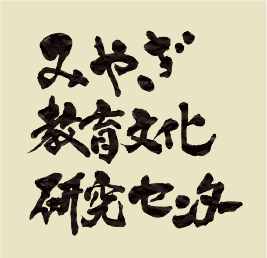『教育』を読む会2月例会
.jpg)
| 日 時 | 2025年2月22日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 『教育』2025年2月号 |
| 内 容 | 【2月号】 特集1では、「被害の歴史」として語られがちな戦争・平和教育に対して、「加害の歴史」や「周辺化されがちな事実」、「加害と被害の重層性」などとどう向き合い扱っていくことが求められているのか。その可能性を考える。 |
| 前回の 様子 |
1月25日(土)、みやぎ教育文化研究センターで『教育』を読む会を開催しました。 |