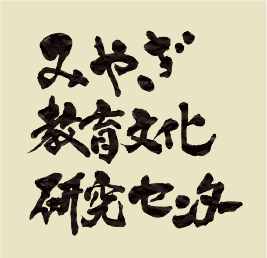『教育』を読む会 11月例会
.jpg)
| 日 時 | 2025年11 月8日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 『教育』2025年11月号(ない方にはコピーをおしします) |
| 内 容 | 【11月号】 子どもたちは今、『子ども期』を豊かに充実して生きているだろうか? 生きることの喜びを感じながら、未来への“憧れ”を持って生活しているだろうか? 子どもが子どもらしく生きることのできる“時間や空間”が、今日の日本社会や学校において、あるいは日々の暮らしの中で、軽視され奪われているように思う。 「余裕がない」という言葉が教育現場を席巻し、そのなかで教師たちは管理の手法で教室を整える。そして、子どもたちは自分の声と身体のさざめきを押し殺し、閉じ込めることを正しいと認識し成長する。教師自身が語れない、聞き取れない余裕のなさから自らを救い出すためにはどうしたらよいのだろうか。
|
| 前回の 様子 |
宮城『教育』を読む会2025年10月例会 10月11日(土)10時~12時に、みやぎ教育文化研究センターで『教育』を読む会を開催しました。 |