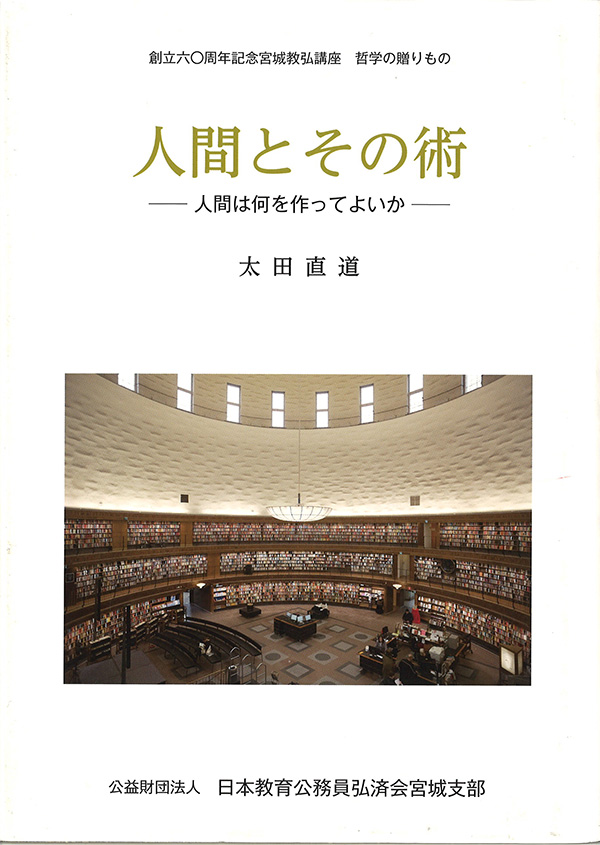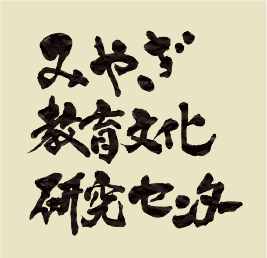2025年4月14日(月)第八講 術と時間ー時間の森を生きる
今回は時間論です。これは、太田先生の一番の関心分野、専門分野だそうです。
私がそうだと強く思ったのは、「時間は狂っている」ということです。時間には物理時間と精神時間があり、物理時間の支配が誕生したのは、西洋近代社会においてです。文明の長い歴史の中ではきわめて最近の事態だというのです。近代工業社会の産物なのです。
現代の私たちが片時も忘れることがない時間というものが、近代以前にはなかったというのは、どういう感覚だったのだろうと考えさせられます。江戸時代にも「子の刻」などの時間概念があったでしょうが、それは2時間くらいの幅があり、今とは全く感覚が違っていたのでしょう。それよりは、「お天道様が真上になったらどうする」とか、「こういう形の月がここに見えてきたらこうする」とかだったのではないでしょうか。そう考えると、月は季節によって、形もでる場所も違いますから、季節季節の月をよく観察して理解していたのかもしれません。
また、時間を表すことばを持たないスー族という人たちがいるといいます。どのように生活しているのか、とても興味が湧きます。
そして、「一つの時間決定(物理時間)が万人を無条件に拘束するというまさにその点において、現代の時間は狂っている」と書かれていました。本当にその通りだなあと思いました。私も現役の頃は、朝起きるときから目覚ましに支配され、学校では分刻みに動き、物理時間に支配され、いつでも忙しく、せかせかと働いていました。立ち止まってゆっくり物事を考える暇もなく、しなければならないことがいつも目の前にあって、何時までそれをやるかばかり考えていたと思います。
太田先生が書いていらっしゃるように「落ちついた時の流れがあるということを知るのは定年を迎えてから」でした。いまは、本当にゆったりと過ごしています。
それからもう一つ興味深かったのが、「本を読むという行動もその人の中で語るということだ」と言われたことです。「読むということは、過去に語られたものと一体になる、飛び込むことなのだ」というのも、納得がいきました。次回は、その語りの話、時間論と物語論です。おもしろそうです。
分からなかったのが、「自己意識」と「精神時間」との関連です。「近代的自我としてのわれわれは自己意識の時間を生きていると考えるであろうが、これは真正の精神時間ではない。」とありますが、よく分かりませんでした。自己意識論を徹底的に攻撃したという「レヴィナスの時間論ノート」要約を渡され一人で読んでみましたが、全く難解でした。来週私は参加できないので、どなたか、教えていただきたいです。(矢部智江子)
|