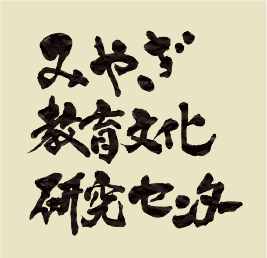三度、福沢諭吉を取り上げました。今回は、まず前々回でも取り上げた『西洋事情』の中から西洋社会における通信・郵便のあり方、国際関係・国際法、さらに庶民への教育と条件整備の必要性を説いた文章を読み、福沢の見識の広さをみていきました。
次に、『明治十年丁丑公論』(1877年)と『瘦我慢の説』(1891年)を取り上げました。前者は福沢が西南戦争に関わって論じたもので、明治維新の立役者であり明治政府のリーダーでもあった西郷隆盛を西南戦争がはじまると国賊として罵言誹謗を浴びせる当時の新聞紙上のジャーナリズムを批判したもの、また政府の役割とその役割を果たさない政府に対する革命論、さらに西郷隆盛に対する福沢の評価についてみていきました。福沢は、全面的に西郷のとった行動をよしとするものではありませんが、当時の世情に対して西郷を高く評価し擁護していると言えます。一方『痩我慢の説』では、まさに江戸無血開城で西郷隆盛と相対した勝海舟についての評価が語られています。福沢は、勝海舟が江戸無血開城によって犠牲を出さずに王政維新を遂げたことを一応評価しつつも、その後も明治政府の要人として分をわきまえない振る舞いは武士の風上にも置けないと強く批判しました。
さらに『学問之独立』(1883年)では、まさに今日の学術会議問題に通じる、学問・教育の国家(政府)からの独立について論じた部分を読み進めました。時の政府に、ぜひとも一読してほしいと思いました。
最後に、1885年3月16日の「時事新報」で論じられた「脱亜論」についてみた。太田先生からは、近年政治学などの分野をはじめとして福沢の差別的・侵略主義的思想のあらわれとして取り上げられているが、福沢は「脱亜」は言ったが「脱亜入欧」とは言っていないこと。また「脱亜論」が論じられるようになったのは戦後になってからであり、それまでは取り上げられることはなかったこと。さらに丸山眞男の説なども引きながら脱亜とは脱・清政府/李氏朝鮮政府、脱儒教主義とみるべきではないかとの補足説明がなされ、近年の一面的な福沢評価でよいのだろうかと話された。
|