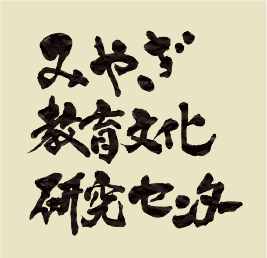未来可能性について考える21
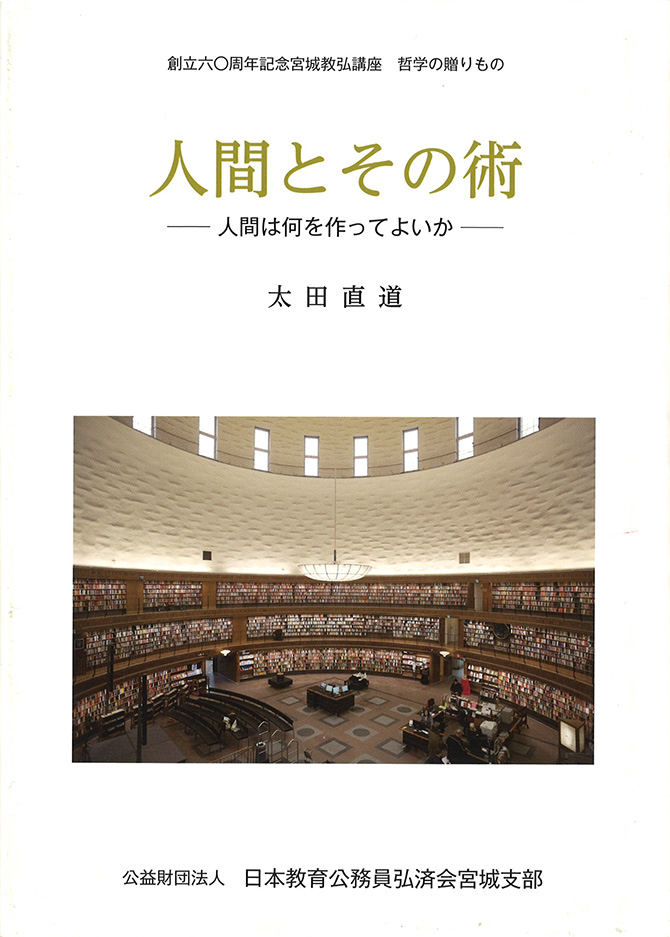
| 日 時 | 2025年4月14日(月) 13:30~16:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 太田直道 著『人間とその術』 |
| 内 容 | テキスト『人間とその術』と太田先生作成の補足資料を読み合い、その内容について意見交流しながら学習して行きます。テキストは、毎回1節ずつ読み進める予定でいます。 |
| 前回の 様子 |
今回は、日本的空間について。日本人の空間意識を律してきたものは内部と外部とのあいだに横たわる境界とオク。人間の生活領域としての空間を内とするなら、それを越えて「オク」へ「オク」へと進むほど空間の聖性は高まり、また秘儀的隠密的空間になる。このようなオク性は、賓客しか通さない奥の間、奥様、大奥、陸奥など日本の空間意識全般に通じているという。 |