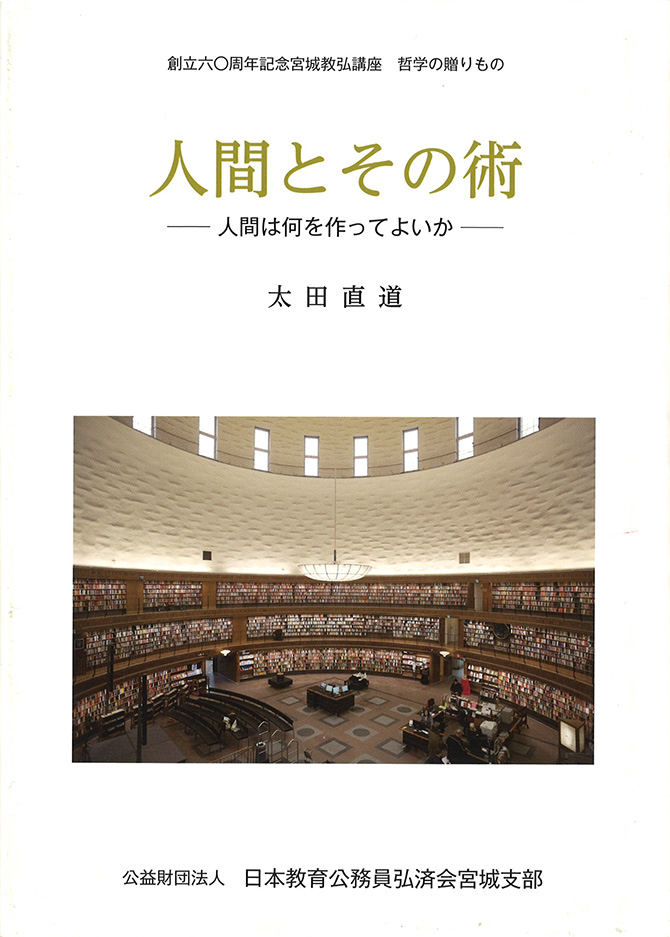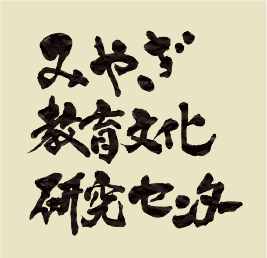前回に引き続いて、人間の生きる空間を取り上げました。今回とり上げたのは「風景」と「家」、それは私たち人間にとって開かれた空間(風景)と閉じられた内部空間(家)と言えます。
風景とは何か。太田先生は、機能的にとらえる前に視覚的にとらえられた「心の制作物だ」という。それは、この世界がものの働きとして把持され現れる以前に私たちの眼前に広がる世界の光景によって見出され、生み出されるものだと言えそうだ。そう考えて、ふと「心の制作物」というのなら、風景でなく情景でもいいかもと思った。風景と情景、あるいは光景はどんな関係に見て取ることができるだろう。またどのように異なるだろうかと頭をよぎった。
一方で、このような風景を見出せないまなざしのあり様を太田先生は、近代の「作図的な機能的透視法」によるまなざしにみる。そのまなざしは、「存在を見ず、機能のみを視野に入れる」ことによって「事物の襞を剥ぎ取り、世界を真っ平ら」に、均質性のもとに平板化し押し延べる。太田先生は、このような近代のまなざしのもとに見出される風景を「殺風景」という風景だという(風景殺しによって見出される風景)。そして現代の私たちはこの殺風景の世界を生きるが故に、皮肉にも逆説的に私たちは野原や丘陵、せせらぎの水辺、田園や里山など山水草木の自然の中に新たに風景を見出し、またそれに魅了されるのである。風景は自然とともにあり、いのちとともに広がる世界と言える。
風景論としてテキストでは、西洋の絵画や東洋の山水画、あるいは花鳥風月の詩歌の世界を取り上げて、西洋における風景と東洋における風景の受容の歴史やその違いなども触れられていて大変興味深かった。
次に家とは何か。テキストでは家について具体的に言及する前に「建てること住むこと」という小見出しで、ハイデガーの『放下』やエリアーデの『聖と俗』の中から文章を引用しつつ、故郷喪失の近代を生きる私たちにとって、いや近代のみならず人間にとって「建てること住むこと」は、この世界に生きていく上での最も基本的な空間的術であること。そして家は「われわれを保護し安らぎを与えてくれる」ものであり、「人間の空間的規定の原理」であるという。テキストではバシュラールやレヴィナス、ボルノー、さらには『星の王子様』の著者であるサン=テグジュペリなどに触れながら、家が外部性の威力から身を守る保護と安らぎの内密な空間であるとともに、世界へと自らをひらき交信する中心であることなどをみていった。
|