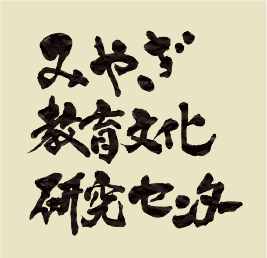道徳と教育を考える会 1月例会(隔月開催)

| 日 時 | 2025年1月20日(月) 13:30~16:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 当日配布 |
| 内 容 | 前回に引き続き、福沢諭吉について学びます。今回は、岩波文庫の『福沢諭吉教育論集』『福沢諭吉家族論集』を取り上げます。太田先生曰く、ぜひ読んでほしいおすすめ本と絶賛。ここからの抜粋資料をもとに福沢諭吉の教育思想、ジェンダー問題・家族論についてみていきます。どなたでも参加できます。興味関心のある皆さんの参加をお待ちしております。 |
| 前回の 様子 |
11月からは、時代が「江戸」から「明治」へということで、その第1回目として「福沢諭吉」を取り上げました。 そのうえで今回は、福沢を代表する主著『学問のすすめ』と『文明論之概略』を取り上げ、その抜粋資料をもとに学びました。太田先生が両テキストから抜粋した個所はもちろん異なり相違しているものの、同時に共通したテーマ・内容にかかわっている点も多くあり、両テキストの抜粋資料から共通に読み取れた点を要約すると次のようになる(主に『学問のすすめ』によりながら)。 |