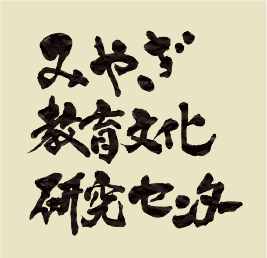『教育』を読む会1月例会
.jpg)
| 日 時 | 2025年1月25日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 会 場 | みやぎ教育文化研究センター 会場の詳細はこちら |
| 参加費 | 無料 |
| テキスト | 『教育』2025年1月号 |
| 内 容 | 【1月号】 特集1では、ICT教育が推進される中で、教えと学びの教育実践がどのように変わり、またそのような変化の中でどう教育実践を創造していくことが求められるのかを考えます。 |
| 前回の 様子 |
宮城『教育』を読む会2024年12月例会の感想 12月21日(土)9:30~12:00に、みやぎ教育文化研究センターで、『教育』を読む会を開催しました。参加者は8名でしたが、活発な議論ができました。 |