2011年12月31日
2011年も今日が最後だ。最近読んだ本に「経済は虚で、環境は実だ」と書いてあったが、私たちを揺さぶった大震災をこの言葉と結びつけて考えつづけている。
こんな時だからか、今年一番私に衝撃を与えてくれた本は、ナオミ・クライン著「ショック・ドクトリン」だった。
著者30代での執筆であり、ここ約30年間の世界の出来事を取材し続けて書いたものだ。チリのクーデター、アパルトヘイト後の南アフリカ、ソ連の崩壊、イラク戦争、中国の天安門事件等々とびまわる。もちろん、9・11もだ。そして、スマトラの津波、ニューオリーンズのハリケーンの地にまで入り込んでいる。2007年に書いているので、3・11は入っていないが、この本をよむことで、読み手の想像は3・11までも十分ふくらんでくる。
私は、テレビ・新聞などで個々の出来事はそのおおよそは知っているつもりでいたが、この本によって、それらの根は同じ糸でつながれていることを知った。言葉を換えれば、今まで個別にしか出来事をとらえていなかった私が、広くものを結びつけてみることのできるメガネを、このグローバリゼーション時代を生きる者として著者からもらったような気がしたのだ。そのメガネによって著者が触れていない同時代の日本の動きも、(ああ、そうだったのか。これが小泉政権だったのだ)とうなずくことができた。何が共通の糸か。まとめることは著者の意図をゆがめるかもしれないが、民営化・規制緩和・社会支出の削減などになるか。
その糸によって世界はどうなっているか。たとえば2006年、「世界の成人人口の上位2%の富裕層が、地球上の世界財産の半分以上を所有している」と国連の調査報告が書いているという。
著者はこの格差をつくったものを「惨事便乗型資本主義複合体」と述べているが、津波被災のタイで、「政府にお金を出させようとして戦っていたときは、自分たちの力で立ち直るために何かしようという気はまったくなかった」と語られたと書き、自力で復興に努める人々に共通する重要な点がある。彼らは異口同音に、自分たちはただ建物を修復しているだけでなく、自分自身を癒やしているのだと言っていたが、これこそ惨事便乗型の対極にあるものとする。これらは、越年し長丁場になる3・11の復興に関して、「あなたたちが大きく試されているのだよ」という著者の強いメッセージにも聞こえる。
2011年12月25日
寒いなか、大田堯先生にも足を運んでいただき、17日に映画「かすかな光へ」上映会が終わった。
今回の上映会は上映実行委員会をつくって取り組んだ。大田先生の長い間の幅広いお仕事に接してお世話になった方の多さを考えると、この方式が一番いいだろうと思っての提案だったがどなたにも喜んでいただき会はスムーズにつくられた。
短期間だったが、実行委員会は準備会を含めて4度もった。そのたびに東北大の学生や若い保育士さんたち、そして中小企業家同友会からの参加と、私たち研究センターだけの取り組みとはまったく違う雰囲気のかもしだされる会となった。
時間がないのでセンターでつくって使っていたチラシについて、「これでは学生は集まりません。ぼくが学生用のものを作って使います」と学生のSさんに言われたこともある。
異なる職種の人や年齢層もさまざまな人で会をつくることの大事さを強く考えさせられた上映会であった。
大田先生は、短時間でも被災地に足を入れることをご希望、仙台駅から直接仙台沿岸部に行ってこられた。会場到着は講演開始予定時間まで10分もなく、少しお休みになられることをおすすめしても、93才の先生は休もうともせず、時間の打ち合せだけでホールに足を運ばれた。
登壇した後、お立ちになったまま東日本大震災へのお見舞いを述べられ、それから用意していた椅子に座られた。
物や金の復興ではなく「生命と生命の絆」の創出であり、「どうなる」ではなく「どうする」の姿勢の大事さを強調、魯迅の「故郷」の最後の一文「もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。」でお話を結ばれた。
若い人の感想が多く残されたのも、これまでにないことだったように思う。
2011年12月20日
読む片っ端から忘れてしまうのだが、未だに本を読まないではおれない。家族には呆れられ総スカンである。本は邪魔物であり、それをいたるところに置きっぱなしにしている私は家ではどうしようもない困り者になっている。
「大学の下流化」(竹内洋)の中に、「1964年に購入された書籍のうち、大学生によって購入された割合は32%である。(略)ところがそれから30年後の1994年になると、大学生の書籍購入割合は8%」と書いてあった。
これを読みながら思い出したことがある。私の学生時代のこと(1954年~58年)だ。
 電力ホールでの文化講演会をのぞいたことがある。作家井上靖と角川書店創設者角川源義の講演であった。
電力ホールでの文化講演会をのぞいたことがある。作家井上靖と角川書店創設者角川源義の講演であった。
その折、角川は、「仙台に来たのは今日が2度目です。1回目は阿部次郎に『三太郎の日記』の出版をお願いに来たのでした。それまでの出版物はことごとく失敗して、最後にかけた1冊でした。それがダメなら自殺しようと思ってのことでした。阿部先生にお許しを得てそれで角川は死なずにすみ、今があります」ということを話した。その時は、出版という仕事はそうなのだと思ったことが大きく、「三太郎の日記」で生き返ったことの驚きはなかった。まだ、その頃、三太郎は学生の体からそう離れてはいなかったのだ。
角川版「三太郎の日記」が世に出たのは、調べてみると昭和25年(1950年)だ。
しかし、今考えてみると、最後の1冊を何にかけるかを考え、行き着いたのが「三太郎の日記」であり、それで生き返った角川書店が今も存在するということを考えてみると、何がよいかどうかはべつにして世の中の動きはずいぶん大きいということを思う。少なくとも、今瀕死の書店が「三太郎の日記」の類で息を吹き返すことは絶対あり得ないことは誰もが思うだろう。
だから今をどうと言うことはできないが、(オレはいい時を過ごしたなあ)と、こんなことからも何となく思う。
2011年12月14日
師走のせいにするわけではないが、日記が日記と言えないくらいにまた間が空きすぎた。
日記を書く暇がないとは言うに恥ずかしく、つまりはうまく仕事が運べないということに尽きる。
先に、戦後教育実践書を読む会の渡部やす子さんの「村の一年生」のことを書いたが、あのおり、渡部さんが話の中で触れたちょっとしたことを書きたいと思いつつ延び延びになってしまった。
というのは、土田さんの仕事を読みながら渡部さんは、なんと今は消えてしまった私たちのつくった生活科教科書の「文の意味がわかった」と言ってくれたことだ。
その教科書の部分をそっくり紹介する。
「たろうは、まいにち がっこうへ いく。/はなこも、まいにち がっこうへ いく。 /ころと みみは、がっこうへ いかない。」
(*「ころ」はたろうの家の犬、「みみ」ははなこの家の猫)。
聞いていて、この教科書つくりに参加したひとりの私はびっくりした。これまで、「この意味がわかった」と言われたことは一度もなかったからだ。
文部省(当時)に検定結果を聞きに行ったとき、調査官は、薄笑いをしながら、「あなたたちの教科書は、あまりに当たり前のことを書きすぎている」と私たちに言ったのだった。渡部さんの話を聞きながら、すぐ、このことを思い出したのだが、これはおそらく検定官だけの思いではなかろうと思っていたので、今になって(ほぼ20年後)、「わかった」と言われたことはたいへんうれしかったのだ。
渡部さんのこの話が、土田さんの実践とどう結びついたことによるのかは聞いていない。
でも、私には久しぶりにうれしい一言であり、教科書づくりの労が報いられる思いのした一瞬であった。
2011年12月06日
3日は「戦後教育実践書を読む会」の3回目。テキストは「村の一年生」(土田茂範)。案内人の渡部やす子さんのテキストの読みと土田さんに関する資料の読み込みが深く、すばらしい内容のある会になった。参加者は少数でもと始めた「読む会」だが、教育実践を考えるにこんな会はめったにないだろうことを思うとたいへん残念だ。
土田さん25歳、はじめての1年生担任の記録である。そのなかの「6月 ひとつの主張」の前半部を紹介してみる。
「さあ、きょうは、お医者さんにみてもらうんだから、出席簿のとおりにならびましょう」
こういうと、出席簿1番からずっとならぶ。
「きょうは、たいそうだから、ちいさいほうからならびましょう」
こういうと、すぐ、ちいさいほうから。こうした整列のしかたから、1年生の団体生活のどだいはきずかれるのではなかろうか。
4月、学校から帰るとき、教室から昇降口まで固定して整列させていた。それが、子どもたちから、
「あそこだけ、いつでもまえがえ。いいなえ」
といわれたので、変更してぎゃくにした。それがややしばらくつづいたら、こんどはまん中にばかりなっている子が、
「おらだ、まん中ばっかりがえ。いつまえにすんな」
といいだした。
「んだら、一日ずつ一番前になることにすんべな」
と、1日こうたいにした。これが、子どもらの整列の土台で、朝会でも何でもこのとおりにならんでいた。
「毎日、顔ぶれがかわるな」
先生がたによくいわれたが、わたしも、はじめはしらないでいた。
子どもらが、自然にきめていったひとつの秩序。これは、みんな平等にしてほしいということのあらわれのように感じられる。子どもといえども、ーー子どもだからこそ、肉体をとおして、平等を主張しているのかもしれない。(後略)
なんてすばらしい教師だろう。整列は小さい順となっていれば、たとえ1年生であろうと「決まっているのだから!」とたいていの教師は子どもに耳を貸さないだろう。ましてや「1日交替」にし、「自然に決めていったひとつの秩序」と見る教師なんて何人いるだろう。しかも、その若い教師のクラスの様子に、「毎日、顔ぶれが変るな」と眺めている教師仲間がいるなんて!
土田さんの資質によることはまちがいないだろうが、それを支える教師仲間の存在、土田さんの所属していたサークル「山形県児童文化研究会」の存在の大きさを忘れてはならないだろう。
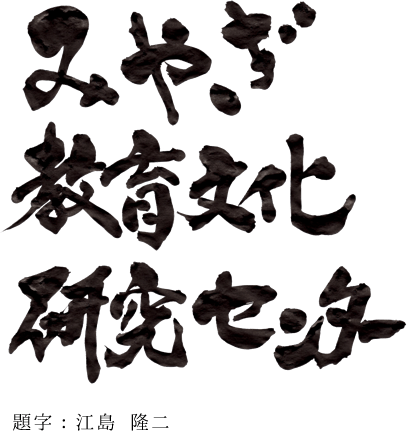
 電力ホールでの文化講演会をのぞいたことがある。作家井上靖と角川書店創設者角川源義の講演であった。
電力ホールでの文化講演会をのぞいたことがある。作家井上靖と角川書店創設者角川源義の講演であった。